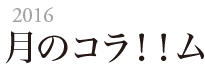2016.12.1
今月のコラ!!ム
「楢山節考」では、70歳になると「楢山まいり」に行くことになります。おりん婆さんも、まだまだ元気なのですが、村の掟に従って山へ行く時を迎えました。村が貧しく、村の縁を守る食い扶持が必要なために、老人は遺棄されるのです。おりん婆さんは、自らこの「楢山まいり」を早めるためにわざわざ前歯を折り、姥捨てを志願します。息子の辰平は辛くてしょうがないのですが、掟に逆らうわけにもいかず、婆さんを背負って山へむかうという話なのですが、この辰平が向かった山を「姥捨山」というそうです。現に、字こそ違えJR篠ノ井線には今もこの「姨捨」という名前が残っています。
私が気になったのは、この棄老伝説が「姥捨て」であって、「爺捨て」といわれていないことです。爺は捨てられなかったのでしょうか?それとも該当する 歳を迎える前に亡くなっていたからなのでしょうか?いずれにしても、私もそんな歳になりました。でも、「どうせ山へ行くなら、美熟女と温泉に浸ってみたい」などと考えている私には、まだちと早い気もします。
さて、今日からは12月、本当に早いものです。この月のことを「師走」と言いますが、今のところ、どこを見ても、お坊さんや先生の走っている姿を見かけることはありません。ところで、この師走という言葉の由来には異説もあって「・・を、し果たす」とういう言葉が訛ったともいわれているそうです。・・には「仕事」や「男性」(いや、さすがにそれはまずい)、「女性」、「学問」など何を当てはめてもいいのですが、まだまだ「・・をし果たした!」などと、したり顔をしないで、大いに惑いながらも、爺捨て山を回避して極楽広場へ直行しようと思っています。
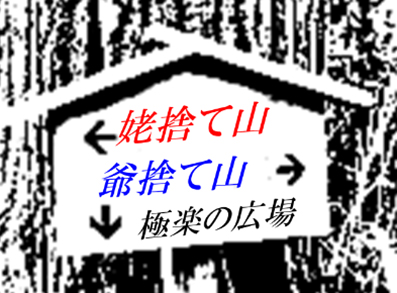
2016.11.1
今月のコラ!!ム
今年もあっという間に11月になりました。本当は、あっという間ではなく、すでに10カ月も経っているのですが、歳のせいか、月日の経つのが年々早く感じるようになりました。まさに、心理的時間の長さは年齢に反比例するとした「ジャネーの法則」通りですね。10歳の人間にとって1年の長さは人生の10分の1程だけれど、70歳の自分にとっては70分の1にしか過ぎないということなのかもしれません。
たしかに、1日より1週間のほうが「早く週末が来ないかな」と短く感じますし、1週間より1カ月の方が、「早く給料日が来ないかな」と短く感じます。もっと言えば、1カ月より1年の方が、「もう誕生日かよ」とも感じたりもします。結局、1番長く感じるのは、妻と「ひたすら平穏であれ」と祈りつつ過ごす1日なのかもしれませんね。
11月の季語は、俳人高浜虚子が「われも亦(また)紅(くれない)なりと ひそやかに」と詠んだ吾亦紅(われもこう)。十五夜の宴で、共に飾られたススキのようには目立たないかもしれないけれど、けなげに咲くこの花のような人生を送りたいものです。この吾亦紅、花穂の上から順に下へ開花をしていくといいますから、これからまた、いいことがあることを期待して!
2016.09.30
今月のコラ!!ム( Ⅱ )
W杯アジア最終予選で、日本はイラクを破り、辛うじて希望をつないでオーストラリア戦に臨むことになりました。本田・岡崎など旧来のメンバーが精彩を欠く中、山口や原口など若いメンバーの活躍によって勝利を得ることができました。90分では1対1のまま決着がつかず、アディショナルタイムで、途中から出場した山口がミドルシュートを決め、これが決勝点になったのです。
サッカーにそれほど関心を持たない私が、こんなことを書くのは、この「アディショナルタイム」という言葉に惹かれたから。負傷者のケガの判断や、搬出などで浪費される時間を、「ロスタイム」というのは知っていましたが、それによって追加される時間のことを「アディショナルタイム」というのは知りませんでした。追加されるのは1分単位で、ルール上は制限がなく、専ら主審の判断に委ねられているのだそうです。タイムキーパーもいません。バスケットにはいるのに。大相撲にだって時計係の検査役がいます。負けたイラクチームの監督が、腹いせ交じりに「主審は日本寄りだった。6分の追加時間は長すぎた」と言っているのは、このあたりの客観性のなさを突いているのかもしれませんね。
でもそんなものは所詮、「敗者の繰り言」に過ぎません。大事なのは「アディショナルタイム」という言葉の方です。「ロスタイム」にはどちらかというと、「失う」とか「浪費」とマイナスなニュアンスが含まれているのに対して、「アディショナルタイム」には「追加の」とか「特別の」というプラスのニュアンスが含まれているのです。
70歳になった今、過ぎ去った日々をただ徒に懐かしみ、回顧にふける「ロス」ではなく、心底を、これから体験する未来になお希望を抱く「アディショナル」なものに変えなきゃいけない!と思いました。でも「それを決めるのはいったいは誰かって?」「主審がいなけりゃ、あなた・主人か、神様しかいないでしょう、間違ってもカミさんではありませんからね!」
今月のコラ!!ム( Ⅰ )
黒門市場を歩いていて、不意に見知らぬ魚屋のおばちゃんから「ええね!昼間っから、ぶらぶらしとったらええねんやから」と声を掛けられ、「誰がぶらぶら歩いとんねんっ!」と見返すと、にっこり笑ったおばちゃんから「これ、持って行き」と言って生魚を手渡され、難儀しながら会社まで持ち帰ったことがありました。また別の日には、行きつけの洋食屋のおやじから、「私ら、先生(なぜか、そう呼んだ。まあ符牒のようなものだろう)みたいに、ええ加減な話しとったらええっちゅうもんと違いまんねん、一所懸命に働かんと!」と言われ「誰がええ加減な話しとんねんっ!」と心の中で反発しつつも、「うまいこと言いよんなあ」と感心したこともありました。さすがに、中島らもさんの本で紹介されている、「ラーメンに虫が入ってる」とクレームを付けた客に、「ええ若いもんが、好き嫌い言うてどうすんねん!」と追い返したおばちゃんに遭遇したことはなかったのですが、東京で外食するたび、このマニュアルにない話のやり取りを懐かしく思い返すことがあります。
思えば70年の人生のうち、大阪・京都と東京ほぼ同じ期間を過ごしているのですが、心の中は今でも関西人ということなのかもしれません。6月に女房とバルト3国へ旅した時も、ずっと一緒にいたのは岸和田のおばちゃんたちでした。ちなみに「大阪人チェック」をしてみると「世界中どこに行っても大阪弁を通す」「おもろないヤツと言われることが、最大の屈辱」「新聞で米朝会談という見出しを見て米朝師匠だと勘違いした」「カレーに生卵をいれるのは普通の食べ方」「お釣りを300円受け取る時、300万円と言われたことがある」「山本さんをや―もっさん、プラスティックをプラッチックと言ってしまう」「笑点の何が面白いのかわからない」など、ほとんどの項目に該当してしまいます。
「ワナカの塩たこ焼き」「二見のぶたまん」「とん蝶」、おいしいものも一杯あるし、人情味もあるし、いっそもう一回大阪へ帰ろうかとも思ったりするのですが、やはりこのまま東京に残ります。室尾犀星も言っているじゃありませんか、「故郷は遠きにありて思ふもの」って。少し離れて、「よかったなあ」と懐かしむくらいが丁度いいのかもしれません。
2016.08.31
気象予報士の進路予想より北上した迷走台風がようやく去って、ホッしていたら、それを上回る規模の大型台風が舞い戻ってきました。先月21日からフロリダ・オーランドへ旅していた嫁がついに帰ってきたのです。彼女が不在の間、せっかく2匹のワンコたちと穏やかな時を過ごしていたのに、またまた喧騒の日々が戻って来るのかと思うと、迷走台風が恨めしく、不謹慎ながら、いっそのこと関東地方を直撃してくれればよかったのにとさえ思ってしまいました。
結局14:30到着の帰国便は17:45成田に到着したのですが、「疲れたから、タクシーで帰っていいかな?それと夕食、私は機内食を食べたからあなたは外で取ってきて!」という電話が入り、行きつけのタバコの吸える喫茶店で食事をして帰ることになりました。昔は夫婦で海外に出る時、歩いて5~6分のホテルからリムジンバスで成田まで行き、帰りはタバコの吸えるタクシーで帰宅するようにしていましたが、タバコが吸えなくなってからは、リムジンバスで帰るのが常だっただけに、よほど疲れていたのだと思います。
私が食事をすませて帰宅すると、ものの5分も経たないうちに嫁が帰ってきました。シートから動かない運転手を後目に、重いキャリーバッグを玄関口まで運び終え、空返事をしながら、ディズニー話に耳を傾けつつ、テレビの画面に目をやるのですが、そんな時に限って、地上波もBSもCSも見たい番組が無いものです。早々にタイミングを計って、ワンコとともに寝室へ避難することにしました。
「夜目遠目笠の内」という言葉があります。「女性の容貌は、夜見た時、遠方から見たとき、笠をかぶっているときに、実際より美しく見える」ことを言うのだそうですが、かくいう私も「嫁を遠目から眺めていた」ほうが本当は幸せなのかもしれませんね。
2016.07.29
タクシーに乗って、運転手さんと会話を交わすうち、たぶん自分より少し上か同年配だと思われる人には、「運転手さんおいくつ?」と聞くことがあります。たいていの人は「もう○○歳になってしまいました」と答えてくれるのですが、先日乗ったタクシーの運転手さんは「いやーもう、恥ずかしくってヒトに言えないくらいの歳になってしまいました。」となかなか答えてくれなかったのです。こちらも多少意地になって更に食い下がると、ようやく「68歳なんです」と明かしてくれたのはいいのですが、何と私よりまだ2つも若いではありませんか。どう見ても自分より年上だと思っていた予想が外れたことと、自分も同じように「ヒトに言えない歳になった」のかということにショックを受けました。
確かに、わが事務所の某池田君のように横綱・鶴竜を「つるりゅう」などと文字を読み違えることは滅多にないのですが、耳から入ってくる言葉を、時として聞き違えることはあるかもしれません。弘兼憲史さんの本のように、「パプアニューギニア」を「パパは牛乳屋」とか「バングラデシュ」を「ぼんくら亭主」などと間違えたり、子供のころ腹をすかして帰り母親に「何か食べるものない?」と聞いて、「台所にパンがある」と答えた母の言葉を、「大都会パートⅡ」と取り違え「誰がテレビの話しとんねん!」と腹を立てたことはありませんが、今でこそポピュラーになった「アベノミクス」という言葉を初めて聞いたときは、「阿倍野へ飲みに行くっす」と勘違いして「ミナミでいいのに、なんで阿倍野なの?」と思ったことはありました。そして今また一つ難儀な言葉が生まれました。熱狂的なブームを巻き起こしている「ポケモンGO」という言葉です。よくもまあ次々と新しい言葉を生み出してくれるものです。私のようなガラケー組には縁のないような気もしますが、若い子はともかく、いい歳をした大人までが熱狂している現象を見るたび、私には「ポケモンGO」が「呆け者の業」に聞こえて仕方ないのですが、やっぱりこれも老化による幻聴というものなのでしょうかね?
2016.07.01
今年100回目を迎える日本陸上競技選手権大会を、といってもテレビで見ていて驚きました。山縣亮太か桐生祥秀の優勝という大方の予想を裏切って、ケンブリッジ飛鳥が一瞬の差で勝利を勝ち取ったのです。見とれたのはその速さもさることながら、走る姿の美しさです。ジャマイカ人の父と日本人の母の間に生まれ、太股を持ち上げ、かつ体幹の安定性を支える大腰筋肉の発達したシルエットはサラブレッド馬のようで、横を走る2人が止まって見えるくらいの疾さでした。180センチを超える鍛え上げた体躯と、彫の深いルックス、まさに新しいスターの誕生の瞬間を目撃したというわけです。日を置いて東京ドームで巨人・中日戦の始球式に臨んだときには、もう観客から声援を浴びるほどの存在になっていました。
芸能界で活躍する「ハーフ・タレント」は今も多いのですが、ここ最近、特にその波がスポーツの世界に波及して、「ハーフ・アスリート」と呼ばれる人たちの活躍が目立つようになってきたように思います。同じ陸上の短距離にはガーナ人の父を持つ高校生、サニブラウン・ハキームがいますし、テニスではポスト錦織と言われるダニエル太郎や大坂なおみ、バレーの宮部藍梨、バスケの中村優香、ラグビーの松島幸太郎、サッカーの鈴木武蔵、相撲の高安、そうそう楽天のオコエ瑠偉もハーフ、枚挙にいとまがないほどの「ハーフ・アスリート」が活躍しています。
運動生理学の権威によると、「遺伝子をミックスすると両親の持っているいいところを足し算していく」ということらしいので、正にハイブリッド効果と呼んでもいいのかもしれません。もっとも、中にはサッカーの下手なブラジル人もいれば、柔道の弱い日本人や面白くない大阪人もいるわけです、ただミックスをすればいいというわけでもないのでしょうが・・・
もし、時間を20~30年ほど前に戻せるなら、ジャマイカ辺りから嫁を娶って、今頃は左うちわで過ごせたかもしれないなんてね。
2016.05.30
週に1~2本しかタバコを吸わないわが事務所の池田君が、「このタバコ、吸ってみませんか?」と白いパッケージの「ウインストン」を出してきました。「ああ、知ってるよ、ウインストンね、あんまりうまくないんだよね。それにこんなパッケージだったかな?何、1ミリ?そんなタバコなんて吸うくらいなら、いっそ吸わない方がましさ」素直に好意を受ければいいものを、そんな憎まれ口をたたきながらいざ吸ってみると、口の中に甘い香りが広がりました。「これって、キャビンじゃないの?」と彼に聞いたのですが、もとよりライト・ユーザーの彼にそんなことがわかるはずもありません。調べてみると、JTはこの5月から「キャスター」と「キャビン」を「ウインストン」ブランドに統合をしたらしいのです。背景には欧米とは嗜好の違うアジア、中でも世界のタバコ消費量の40パーセントを占める中国マーケットを視野に入れた戦略らしいことが分かってきました。どうやら、JTは世界的にネームバリューのある「ウインストン」のバリュエーションに、同じアジア人である日本で長く愛されてきた「キャビン」や「キャスター」を加えて、アジアへの進出を図ろうと考えているようです。勝手にタバコの名前を変えたり、値上げをしたり、ブランドを統合したり…そんなJTの姿勢に腹をたてつつ、それでもタバコを止めようとは思わないところが、喫煙族の辛いところ。甘い香りにつられて、「うん、これもいいかな」なんて日和ってしまいました。さっそくタバコ屋へ行って「ウインストン・キャビンテイスト」を買おうとしたのですが、あいにく5ミリまでしか作っていないとのこと。仕方なく10ミリのある「ウインストン・キャスターテイスト」を買ったのですが、そのパッケージには「ロングテイスト」~特別巻紙で長い時間タバコの味が楽しめる~と書かれています。本当かな?と思って吸ってみたら、さほどの違いはありません。またしてもJTにしてやられました。こうなりゃ、せめてこのタバコでも吸って、せいぜい「ロングテイスト」な人生を目指すことにでもしましょうかね!
2016.05.02
区役所から手紙が来て、開封してみると「東京都シルバーパス発行」のお知らせ。港区のコミュニティバスばかりか、公衆浴場までが無料で利用出来るらしい。一瞬、ラッキーと思ったのだが喜んでいる場合ではない。むしろ、「もうそんな歳になってしまったのか・・」と落ち込んでしまった。そんな折、あるビジネス情報誌を手に取って見ていると「中折れ現象」という文字が目に入ってきた。「おいおい、シルバーパスに続いて中折れかよ!」落ち込んだ気分をさらにダメ出しするかのような活字に、腹をたてつつ読み進んでいくと、どうやらこの記事でいう「中折れ」とはED、つまり○○不全のことではなく、郊外の人口動態が私鉄を揺さぶり始めたということらしい。つまり、自治体自体は消滅しないのだが、乗客が乗る赤字区間の鉄路は将来的に確実に消滅し、快速や急行などの終点が都心に移され、以遠は普通電車が中心になるため、ドル箱の通勤用急行・快速路線が途中駅までとなることを指すと解った。「中折れ」個所は駅周辺にタワーマンションが建つか否かで解るそうだが、幸いタワーマンションが多く建っている我が家の辺りは大丈夫らしい。最後に、この記事は「都心好きである外国人の投資対象は、山手線ターミナルから急行一駅区間だけと言われ、中折れどころか沿線の先っぽだけになる」と結んでいるが、「中折れ」といい「たつ」といい、あげくの果てに「先っぽ」とまで。紛らわしい言葉をここまで多用する必要があるのだろうか?きっと本人は得意気に書いたのだろうが、○○不全に悩む初老の男性記者であるような気がする。えっ、私?私はEDなんかじゃありませんよ!私は立派なEF(Erectile Function)ですよ。もっとも、最近使う機会もめったにないので「錆びたナイフ」気味ではありますが・・・
2016.04.01
ストックが切れそうになったのでタバコを買いに行き、コンビニの店員さんが「明日(4月1日)から上がるんですね」とさり気なくつぶやいた一言で初めて値上げされることを知りました。「聞いてないよ!」そんなこと。あずきバーはともかくガリガリ君は食べなくてもいいんだけど、またしてもタバコの値段が上がるとは許せない。IKKOさんじゃないけど、「どんだけ~」って感じです。いっそ止めてしまおうか、世の中禁煙ブームだしなあ、喫煙スペースもどんどん減っているし。いやブームに押されて止めるというのもいかがなものか?値上げされる都度、そんな思いに駆られたりするのですが、結局は止められず、というより喫煙することを選んで今日まで来てしまいました。
なんといっても、気に入らないのは他の商品の値上げに隠れて、きちっと告知をしなかったことです。まさか、喫煙族はこれくらいの値上げでタバコを止めらまい、などと高を括っているわけでもないでしょうが、世間ではこれを「どさくさ紛れ」といいます。
この、「どさくさ」とい!う言葉は、江戸時代に佐渡金山の人足を集めるための手段として博徒狩りが行われていた際、役人が踏み込むと四方八方へ逃げ回る者と追いかける者とで賭場が大混乱に陥る様子を、佐渡をひっくり返して「どさ」、それに「○○らしい」などを意味する「臭い」の「くさ」をつけて「どさくさ」と表現したことに由来するといわれています。
どさくさに紛れて自社の商品やサービスの値を上げをする企業には、逆に消費者の方が音を上げてしまうような気がするんですけど!今度こそ本当にタバコを止めてみようかな?
2016.03.01
(その1)
涙ながらに不倫を釈明する某落語家さんの会見を見て、なぜか「壇蜜」、いや「断捨離」という言葉が頭に浮かびました。「断捨離」とは、不要な物の数を減らし、生活や人生に調和をもたらそうという流行の生活術や処世術のことで某落語家さんもこの顰(ひそみ)に倣ったところ、相手の女性の側から思わぬ反撃にあったものと思われたからです。もとはご自身が蒔いた種とは言え、テレビで涙の釈明会見まで強いられるとはお気の毒なことではあります。
でも、言いたかったのはこの某落語家さんのことではありません。「断捨離」のことです。2010年の流行語にも選ばれたこの言葉、近年では実践する人を「ダンシャリアン」や「ミニマリスト」と呼ぶほどに普及しているのだといいます。確かに同感できるところも多いし、モノばかりではなく、考え方や欲望にも応用できるとは思うのですが、そのドライさを人間関係にまで持ち込むというのはどうだろう?如何なものかと思います。
そこで「断捨離」の反対語というのを考えてみました。「断つ」の反対は「継ぐ」、「捨てる」は「拾う」、「離れる」は「接する」、合わせて「継拾接」となります。「見合い結婚は冷たく始まるが熱くなり、恋愛結婚は熱くなるが次第に冷めていく」という言葉もあります。
人間には感情というものがあって、たとえ婚姻関係にはなくとも、自分と相手方の双方が納得していればともかく、ただ熱が冷めたからといって、その都度に断ったり捨てたり離れたりしていたのでは、いたずらに相手方の感情を損なうばかりなのではないでしょうか。冷めたスープをホットプレートで少し温めるくらいの配慮も、時には必要なのではないかと思います。これ、件の落語家さんの話じゃありませんよ。あくまでわが身に置き換えてのたとえ話ですので、くれぐれも誤解なきように!
(その2)
ワイドショーの天気予報を観ていたら、気象予報士が「冬の4K」と言っていました。「寒・強風・乾燥・快晴」のことです。なるほど今朝の出勤時は寒く、風も強かった。うまいこと言うなと感心しました。近頃はワイドショーの中でも天気予報の占める比重が高くなり、単なる予報だけではなく、気の利いたコメントが求められるようになったのかもしれません。私の悪い癖なのかもしれませんが、こういうのを聞くと直ぐに自分なりの4Kを考えてしまうのです。私の4Kは、「緩・京風・完走・改姓」といったところですかね。余りこだわらないで緩-く、あくまでも京の雅を忘れず、与えられた人生を走り切り、万病院克服大居士と改姓して極楽へ旅立つ。どうでしょうかね?
テッセイという会社があります。正式な社名はJR東日本テクノハートTESSEIという新幹線車両清掃の専門会社ですが、かっては「キツイ・キタナイ・キケン」という3Kの代表的な職業とされ、職場のモチベーションも低く、離職率も高い会社だったのですが、その様子を見た上層部がこのままではいけないと、10年前、我々の仕事は清掃業ではなくサービス業です。あなた方は掃除のおじちゃん、おばちゃんではなく、新幹線劇場のキャスト。お客様に温かな思い出をお持ち帰りいただくのが仕事です。同じ3Kでもこれからは、「カンシャ・カンゲキ・カンドウ」を目指そうじゃないかと社内改革に努め、今では奇跡の職場と呼ばれ、国内外からの視察や研修依頼が絶えないほどになったといいます。言葉を置き換えることによって自らの仕事を再定義したのです。
お仕着せの言葉をただ唯々諾々と受け入れるのではなく、自分なりにアレンジしてみるのも面白いかもしれませんね。
2016.02.01
(その1)
さて、二十四節気の初め、立春の候となりました。今の暦では新しい年が明けてからひと月ほどして巡ってきますが、旧暦時代は立春のころに元日が来るように調整されていたといいます。つまり、立春は春の初めであると共に一年の初めでもあったわけです。新しい一年は元日と立春の朝に始まり、次の元日と立春の前夜に終わり、元日の前夜を大晦日、立春の前夜を節分と呼んだそうです。この年という時間のつなぎ目の大事な夜に、年の神が入れ替わるすきを狙って邪悪な鬼どもが悪さをするのを防ぐために豆を撤いて追い払うのが「鬼やらい」で、無防備な年のつなぎ目の夜を守り、新しい年を迎える行事なのだといわれます。いただいた豆を撤かずに年の数以上に食べてしまった私は、せいぜい「福は外、鬼は内」にならないよう気をつけなくてはいけませんね!(たしかに鬼は内にいそうだけれど・・・)
そして節分の一夜が無事に明ければ立春。しかし、春とは言ってもまだまだ寒い最中。早春賦に詠われている「春は名のみ」とはこのことです。でも、これを裏返せば、たとえ「名のみ」でも春は春ということでもあります。昔から日本人は立春を迎えると、いくら寒風が吹きすさんでいようと、雪が降りしきっていようと、その向こうに春の証しを探ってきたことを思えば、少しくらいの辛苦にも耐えられるのではないでしょうか?かの琴奨菊だって、長い冬の時代を経てあんなに素敵な奥さんをゲットできたのだから。それにしても羨ましい!
(その2)
文化は誤用から発達していくことが多いといいます。特別なことが繰り返されていくうちに、いつしか当たり前になってしまうのが、その道筋の一つと言えるかもしれません。「あたりまえ」という言葉も、当然の然の字が誤って前となって、当前だから当たり前になったと言われています。この当たり前感覚が我々の周辺を覆っています。たとえばトイレ。今やウオシュレットが当たり前で、外国へ行ったときには戸惑います。最初はお尻を洗う気持ちの悪さに戸惑ったものですが、いつしかそれに慣れてしまって、今やウオシュレットが当たり前で、従来型のトイレはよほどの田舎か一部の公共施設でしか見かけることはなくなりました。
テレビのリモコンにしても、昔はわざわざ受像機の前へ行ってカチャカチャとチャンネルを回さないといけなかったのですが、今やリモコンでピピッとやれば画面は切り替わります。いまだに「チャンネル回して」なんて口走る人がいますが、そんなことを言えば石器時代人のように白い目で見られるのがオチです。最近では携帯電話、今や私のようにガラケーを持っている人間はほとんどなく、地下鉄や人前で出すのは憚られるくらいスマホ一辺倒の時代になりました。慌ててドコモショップへ行ったのですが、「お客様はそのままの方がいいと思います」と断られる始末。目下何が何でもドコモから変えてやると奮闘中ですが、反面このままガラケーでもいいかとも思っています。
考えてみれば昔はこんなものはありませんでした。子供のころは電話のない家庭は住所録に「呼び出し」などと書かれていたように思います。我が家の電話も最初はハンドルを回す手動式、これは嘘ですが、たしかダイアル式だったと思います。それがプッシュホンになり、各々が携帯を持つ時代になりました。それはそれで便利ではあるのですが、いつしかそれが当たり前になって、いまやスマホ・シンドロームの様になってしまっているのは如何なものかと思います。eコマース・eライフ・eビジネス・eメールなど何かとeばやりの昨今ですがそろそろe加減にしませんか。煽られることに慣れてしまって、それが「当たり前」だと前のめりにならないで、ちょっと遅れ気味の方がいいってこともあるような気がするのですが。
2015.12.30
あろうことか、年の瀬にテレビが故障した。朝いつものように7時のNHKニュースを見ようとテレビをつけたのだが、映像は映らずただ音声が聞こえるのみ。前夜、「アウトレイジ」なる駄作を見てしまったためにテレビが気を悪くしたのかとも思ったのだが、どうやらそうでもないらしい。このままでは大晦日のボクシングや正月の箱根駅伝も見られない。寝室にもテレビはあるけれど、やはりリビングで大画面を見ないと迫力に欠ける。焦ってJ:COMに電話して係員に来てもらったが、回線の不具合ではなくテレビ本体の故障だとか。そういえばメーカーさんからいただいてもう9年ほどになる。当時はまだ42インチの大画面がまだ珍しく、スポーツ番組などを見るたびその臨場感に魅せられた記憶がある。すぐさま赤坂見附にあるビックカメラまで飛んで行き4Kの55インチテレビを購入、本日設置を終えて事なきを得た次第。いきなりクリアになった天童よしみのアップを見た時はさすがにきつかったが、それもいつか慣れるだろう。
だが、言いたかったのはテレビのことではない。この顛末の中で調査に来たJ:COMの係りの人に、「故障の前に何か兆しは無かったですか?」という一言である。「そういえば画像が少し荒くなっていたかもしれない」「スイッチを入れてから画面が出るまでのタイミングが心なしか遅くなっていたかもしれない」指摘されて初めて気がついたのだが、どうもそんな気がする。いつのまにか物事に慣れてしまって、感受性や兆しを読む力が鈍っていたのかもしれない。むかし、第一線で体を張っていた頃はもっと感受性に富んでいたように思う。身体についた脂肪を気にするばかりではなく、むしろ脳や心についた脂肪こそを気にしなくてはいけなかったのではないだろうかと気付かされた。
来るべき新年には、「兆しを読む力の復活」をテーマに掲げよう!溢れるばかりの情報とやらに流されず、この現象の中にある兆しは何なのかを真摯に見つめる事から始めてみよう。KIZASHIは「兆し」でもあるし、「気指し」でもあるのだから。